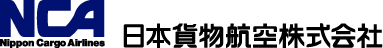2018年8月17日
事業改善命令及び業務改善命令に対する改善措置の提出について)
日本貨物航空株式会社は、本年7月20日に国土交通大臣から受領した「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令及び業務改善命令」(国官参事第390号、国空機第404号)に対し、背景や問題点・要因を分析の上、本日改善措置を国土交通大臣に提出致しました。
今回の行政処分を受けるに至ったことは、航空運送事業に対する信頼を失墜させ、また、関係する皆様に多大なるご迷惑をお掛けするところとなり、深くお詫び申し上げます。このような事態を二度と引き起こすことのないよう社長以下、全ての役職員が一丸となり「一から再生」する気持ちで、法令・規程類の遵守と安全意識の再徹底をはじめとした改善策を確実に実行して参ります。
なお、弊社機材につきましては全11機中2機が運航再開しており、残り9機は機体の健全性を確認し耐空検査を受検後、順次復帰予定です。
本日提出の主な内容及び役職員の処分等については、下記のとおりです。
記
1. 主な問題点と要因
社内調査委員会による調査、及び第三者の立場から監査を依頼した全日本空輸株式会社(以下ANA)による検証等を受けて、今回の行政処分に至った背景や問題点を以下のとおり分析した。
(1) 整備部門の背景要因に対する対策不足
2007年7月の自社整備体制確立後、ボーイング747-400Fを運航していたが、2012年よりボーイング747-8Fを順次導入したため、1機種に比べ整備業務量が増加した。また機数についても、2011年度に比べ2016年度は約1.6倍の機数を運航していたにもかかわらず、整備部門の人員数は、微増にとどまっていた。結果として、運航規模に比べ整備部門の人員数が徐々に不足していった。
(2) 整備現業部門へのサポート不足
このような業務量増加のため、整備部門のマネジメント層・スタッフ部門が整備現業部門を組織的に十分サポートできなくなり、整備現業部門からの信頼低下、独自判断・解釈を行う環境が醸成された。そのような中、経験・知識を有する者の権威が高まり、経験者への意見が言えない組織風土が生まれ、その結果として整備記録の改ざん、隠ぺいにつながった。
(3) 不十分な厳重注意の対策
2016年10月に国土交通省から厳重注意を受けた事例の対策が効果的に機能しなかった原因は、問題発生の背景把握もふまえた対策が適切に行われなかったことが挙げられる。特に役職員の安全意識とコンプライアンス意識の徹底について、知識付与にとどまりそれを個々の実行動として定着させるための施策がなされなかったこと、また厳重注意に至った事象について個人が特定されることを過度に恐れたことから具体的な事例共有が全社で行われず、全社員への情報共有、意見聴収が行われなかったことが考えられる。
※ Maintenance Operation Center: 24時間体制で整備支援を行う部門
(4) 耐空証明の有効期間の変更への対応
耐空証明更新受検を確実に実施する体制を構築し、全機の耐空検査受検(連続式から有効期間1年への変更)を速やかに実施する。
(5) 航空機構造修理の委託体制
自社航空機における機体構造に関する整備作業への対応は、自社における体制の再構築が完了するまで、香港の整備会社(HAECO)及び台湾の整備会社(EGAT)による委託体制を継続するとともに今後は、迅速性の観点よりANAの支援を受ける予定である。
3. 今後の進め方
これらの改善措置は、取り組み実施後の評価及び現在継続中の社内調査委員会による最終的な調査結果等に基づき、内容の見直しを適宜行い、安全文化の更なる定着及び安全管理システムの継続的な改善に取り組んでいく。
代表取締役社長 大鹿 仁史 30%減給 (本年9月より3か月間)
代表取締役専務取締役 佐髙 圭太 30%減給 (本年9月より3か月間)
整備担当執行役員 松田 喜代治 (本年8月末日付け)
(2) 社員
対象社員について懲戒規程に則り厳正に対応